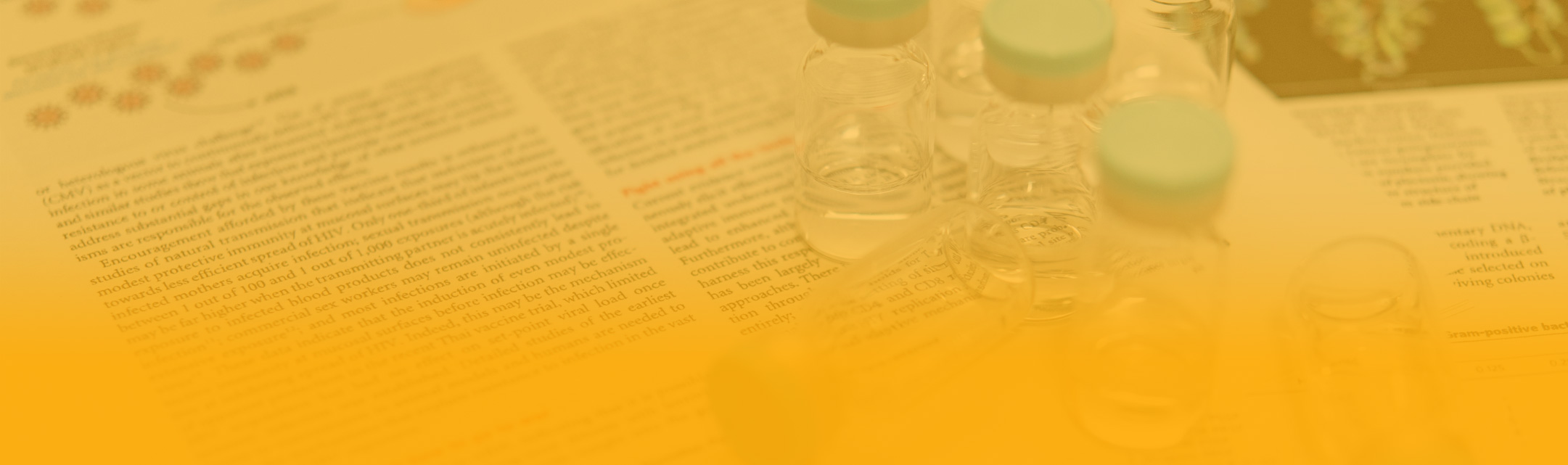重症喘息患者における生物学的製剤導入群と非導入群との経口コルチコステロイド減量効果
Akihiko Tanaka, Mai Takahashi, Ayako Fukui, Yoshifumi Arita, Masakazu Fujiwara, Naoyuki Makita, Naoki Tashiro
| 題名 | Oral Corticosteroid Reduction Between Biologics Initiated and Non-Initiated Patients with Severe Asthma |
|---|---|
| 著者 | Akihiko Tanaka, Mai Takahashi, Ayako Fukui, Yoshifumi Arita, Masakazu Fujiwara, Naoyuki Makita, Naoki Tashiro |
| 出典 | Journal of Asthma and Allergy |
| 領域 | 喘息 |
J Asthma Allergy. 2023 Aug 14:16:839-849. doi: 10.2147/JAA.S411404. eCollection 2023.
目的
いくつかのBIOのOCS減量効果(sparing effect)は臨床試験で示されているが、実臨床におけるBIO導入患者とBIO非導入患者のOCS減量効果を評価した研究はない。今回、実臨床における重症喘息患者において、BIO導入群と非導入群間でOCS1日維持投与量がどの程度減少するかを比較した。
対象と方法
本レトロスペクティブコホート研究には、メディカル・データ・ビジョンのDPC(診断群分類包括評価=Diagnosis Procedure Combination)データベースのデータを使用した。2015年12月から2020年2月までにOCSを継続使用した重症喘息患者を抽出した。主要評価項目は、第0週から第24週までのOCS 1日維持投与量の減少割合とした。解析は逆確率重み付け法を用いた。
結果
合計2927例が組み入れられた(BIO導入:239例、BIO非導入:2688例)。指標日から第24週時点のOCS 1日維持投与量の減少割合の調整中央値(四分位数[Q]1-Q3)は、BIO導入群で25.0%(0.0-100.0%)、BIO非導入群で0.0%(0.0-83.3%)であった(Hodges-Lehmann推定値[95%信頼区間]、0.0000%[0.0000-0.3365%])。指標日から24週目におけるOCS1日維持投与量の減少を達成したBIO導入群およびBIO非導入群の患者の割合は、それぞれ0%以上減少:56.6%および44.1%(オッズ比[OR]1.6554)、25%以上減少:50.5%および40.6%(OR 1.4888)、50%以上減少:42.8%および33.7%(OR 1.4714)、100%減少:26.2%および24.4%(OR 1.1005)であった。
結論
重症喘息患者において、OCS1日維持投与量はBIO治療により減少した。BIO導入群では、非導入群に比べてOCS減少率が75%以下であった患者の割合が高かったが、OCS減少率に明確な差は認められなかった。今回の調査結果を正しく評価するためには、より長い観察期間と本研究から除外された変数を組み込んだ追加の研究が必要と考える。